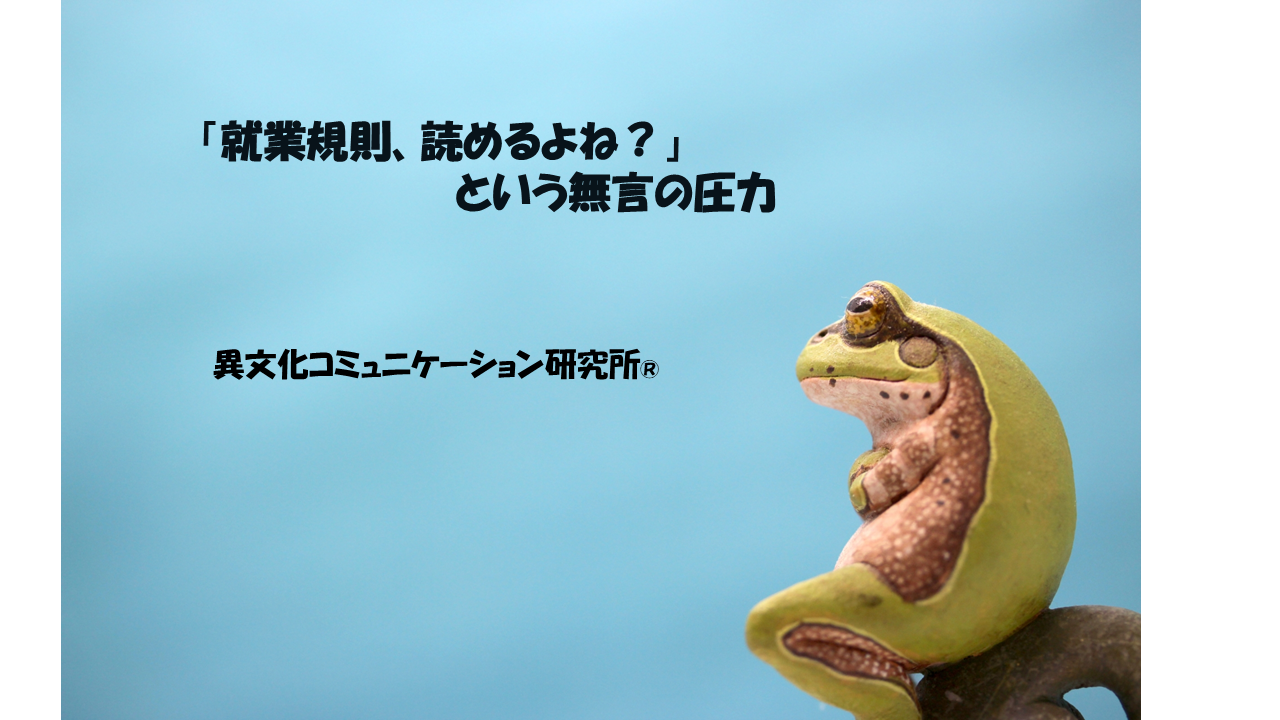
「就業規則、読めるよね?」という無言の圧力 〜外国人社員と“書類の壁”〜
こんにちは、「考えに耽るカエル」です。
今回は、ある企業が初めて『globalforce(高度外国人材)』外国籍の優秀な社員を迎え入れた際に直面した、ちょっとした“すれ違い”のお話です。
■ 初日から始まった「沈黙のトラブル」
とある製造業の中堅企業。
グローバル化の波に乗り遅れまいと、初の外国人エンジニアとしてインド出身のアディルさんを採用しました。履歴書は申し分なし。オンライン面接も好印象。社内の期待も高まっていました。
そして迎えた初出社の日。
人事担当者は、アディルさんにこう伝えます。
「こちら、就業規則と福利厚生のご案内です。あと、社内の安全マニュアルも入ってます。全部で80ページほどですが、一通り目を通しておいてくださいね。」
アディルさんはにこやかに「OK!」と答え、その分厚い資料を丁寧に受け取りました。
しかし、その笑顔の裏にあったのは――
「これは…たぶん、読めないぞ」という、静かな絶望だったのです。
■ “OK”と言われて安心してしまう日本人
アディルさんの日本語レベルは、日常会話や社内チャットには問題ないN4程度。
お昼の注文や軽い雑談には困らないけれど、「懲戒処分とは」「年次有給休暇の取得条件とは」など、いわゆる“会社のルールブック”の言葉はまるで異世界の呪文のようでした。
しかし、日本人の担当者側にはその温度差が伝わりません。
「日本語話せるって聞いてたし、理解できるでしょ?」
「本人もOKって言ってたし、問題なかったと思うよ」
“OK”の一言で安心してしまうのは、日本人あるあるかもしれません。
けれど、「読みました=理解しました」ではない、という当たり前の前提が、採用現場ではしばしば抜け落ちてしまいます。
■ 書類の「日本語」は、実はかなり難しい
就業規則やマニュアルの日本語は、いわば“法律寄りの文体”です。
漢字が多く、長い文、硬い語彙、抽象的な言い回し――
これは母語話者でも「読む気が起きない」文章なのに、第二言語の人に丸投げしてしまうのは、なかなかの無茶ぶりです。
しかも多くの企業では、「理解できているかどうかの確認」はせず、「説明責任は果たした」ことで完了扱いにしてしまいがちです。
■ では、どうしたら良かったのか?
実は、この企業ではその後、小さな改善を積み重ねることで、大きなトラブルを未然に防げるようになりました。
✅ ポイント1:要点をまとめた簡易バージョンを用意
「フルバージョン」とは別に、A4一枚でまとめた“やさしい日本語”の要点資料を作成。イラストやフロー図も活用し、パッと見て概要がわかるようにしました。
✅ ポイント2:オンボーディングで通訳サポート
初日のオリエンテーションには、英語が堪能な社内スタッフが同席。説明の合間に補足翻訳を入れることで、本人の理解度を確認しながら進めるスタイルに変更。
✅ ポイント3:「聞き返せる空気」をつくる
「何かわからないことがあったら、いつでも聞いてね」という言葉を形だけでなく、本当に“聞ける空気”として伝えるために、ランチタイムや雑談の中で声をかけ続けました。
■ 「伝えたつもり」が一番危ない
今回のエピソードは、いわば“あるあるの第一歩”です。
「悪意はない」「本人もOKと言ってた」――でも、トラブルは起こる。
だからこそ、言葉や文化の違いに配慮する以前に、「相手が理解しているか」を丁寧に確認することが、何よりも重要です。
■ カエル的まとめ 🐸
✔ 書類は“読めるか”だけでなく、“伝わっているか”を基準に
✔ 日本語ができる=就業規則が読める、ではない
✔ 「説明して終わり」ではなく、「確認して完了」へ
島崎ふみひこ
異文化コミュニケーション研究所(R)
https://www.globalforce.link/
日本企業のダイバーシティ教育、高度外国人財の採用・活用