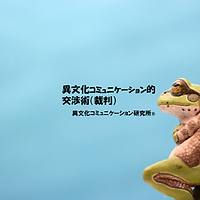
異文化コミュニケーション的交渉術(裁判)
キリスト教や、イスラム教のように、ただひとつの神を信仰する宗教を『一
神教』と言いますが、その人たちは、判断を神に委ねることをよくします。
アメリカで生活をしていた友人が、借家の修理を家主に依頼したところ、意
見が食い違いトラブルになって「裁判」になってしまったことがあります。
日本でなら、まずはいろいろと話し合いをした上で、解決しない場合に裁判
を行いますが、そのアメリカ人の家主は大した交渉もせずに裁判に話を持っ
て行ったそうです。
裁判の当日、裁判所の前で遭遇したそうですが、「喧嘩腰」かと思いきや、
ニコニコと握手を迫ってきて「元気にしていますか?」と普通の会話をしに
きたというのです。
私の友人はとても驚いておりました。
その裁判の結果まで私は記憶していないのですが、友人はそのままその家で
暮らしていたので、穏便に解決したのだと思います。
『一神教』を信じる人たちは、最終的な判断を「神」に委ねることをする傾
向があるように感じます。
お互いに自分が「正しい」と主張し合う場合、客観的で絶対的な「神」の存
在があれば、平穏な気持ちでいられます。判断は「神」に決めてもらえばよ
いのですから…。
『一神教』の人が多い国における裁判の場は、そのような「場」に近いと考
えているように感じます。どうもそこには「愛」さえ感じます。
アメリカのテレビ番組に公開裁判(?)的なものがありますが、番組の演出かも
しれませんが、まさにそこには「愛」を感じます。
そう考えると、角と角を突き合わせる場でも、お互いに冷静にいられます。
『裁判所』のことを英語で”court”と言いますが、その言葉には、宮廷、御殿
という意味があったり、テニスコートといった使い方をすることから、私た
ちの持っている「裁判」対するイメージとは異なったものを彼らは持ってい
るのかもしれません。
「裁判」が必要な場になっても、恐れず「愛」をもっていること、そして正
義を尽くした後は、判断を委ねる気持ちでいれば、結果を受け入れやすいか
もしれません。
島崎ふみひこ
異文化コミュニケーション研究所(R)
日本企業のダイバーシティ教育、高度外国人財の採用・活用